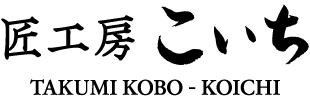「この肉髻珠の部分に宝石や水晶が埋め込まれるんです」と、絹本封印が終わった阿弥陀如来像から頭の前の丸い部分を取り外される仏師の先生。
「にっけいしゅ・・・???」
正直、先生や親方に一度聞いただけで覚えられるほど良い頭じゃないので、教えていただいたお話と調べた内容をまとめて、備忘録的に綴っておきたいと思います。
一晩寝たら絶対に「ブツブツの真ん中にあるちょっと大きいやつ」みたいな感じの名前になってるはずです。それこそ頭の形が良くないせいか?かといってこの頭の形になりたくは・・・
(無知ゆえに間違っていたり、失礼な言い回しをしてしまっていたりするかもしれませんが、何卒ご容赦くださいませ〜)
肉髻(にっけい)
え〜、これってコブからきてるんですか!ブツブツ(螺髪)のことじゃないですよ。頭の形がやんわりした凸型になってるじゃないですか、その頭頂部付近の凸ってる部分のことです。てっきり髪の毛のブツブツ的にそうなってるのかと思ってました。
『肉髻』これは、頭がコブ状に盛り上がった形で、如来のみが有するものとされていて、悟りを得た存在である証であり、智恵や徳を象徴するものなんだそうです。確かに、漢字を見ても『髻(たぶさ:髪を頭上に束ねたもの)』の前に『肉』がついてますもんね。
ちなみに、菩薩像の場合の凸部分は、宝髻(ほうけい)と呼ばれる結われた髪の毛なんだそうです。だからややこしくて混同しちゃうのかもしれませんね。
そして、三十二相(さんじゅうにそう)の一つで、、、 って説明があっても、今度は「三十二相って何ですか?」ってなっちゃいます。
この世のすべての真理を体得した存在であることを示す、32の特別な特徴のことなんだそうですが、最初に何を見聞きしていたのかわからなくなりそうなので割愛させてもらいます〜苦笑。

肉髻珠(にっけいしゅ)
仏の智慧の象徴である肉髻の前の真ん中部分にある、螺髪よりちょっと大きく見える突起部分が『肉髻珠』で、智慧が極まった証として現れる、光の珠(たま)なんだそうです。頭部地肌の真ん中が盛り上がって見えてそれが朱色だったことから、朱色の珠や宝珠で表現するようになったとも言われていたりするようですが。。。
ん〜、、、肉髻珠=智慧の頂点の象徴!みたいな感じで覚えやすく要約させてもらっていいでしょうか〜苦笑。
知恵じゃなく、『智慧』、悟りの力・本質を見抜く力の精神的領域であることはちゃんと抑えておきますんで〜!
なんか個人的には、眉間のとこ以外にそんなのあったっけ?とか、白毫(びゃくごう)と呼ばれてる部分とごっちゃになってました。
私なんかがどうあがいたって、突出した頭にはなれませんが、螺髪に覆われていながらの一体化したこの自然な隆起、仏師の先生とこの阿弥陀如来像に頭が下がるばかりです〜